Chapter 1
「アグネス、大変よ」
「どうした?」
「《ユーザー》がダウンロードしたあのゲーム、中身はウイルスだったの」
「なんだって!?」
他のプログラムがノックもせずに駆け込んできたのは、部屋でひとりの時間を満喫している時だった。
一流のセキュリティソフトウェアとして、メモリ内の私のセグメント領域は厳重に守られている。ただ、緊急事態に備えて、いくつかの信頼できるプログラムには立ち入りの権限を与えていた。今入ってきたこの子もその中の一つで、『QuilleWriter』というワープロソフト。略して「クイル」と呼んでいる。
「最初は普通に起動したのだけれど、偽装だったみたいね。ハードディスク内のファイルをどんどん勝手にスクランブル化しているわ」
「被害状況は? 重要なファイルは無事か?」
「やられたのは『学校関係』フォルダの一部だけね。今のところ」
「システムファイルまでは来ていないのか?」
「それは無事。定期デフラグ前だったのが幸いしたわ……そうでなければ、もっと深刻な事態になっていたはずだから」
「喜ぶのはまだ早い。とにかく、今すぐ現場に行ってウイルスを退治するぞ」

ベッドから飛び降り、左手を愛用の武器《サイズ・ブルーム》にかざす。すると、ほうきと鎌が合体したかのようなそれが手の中に吸い込まれていく。
「イエス、マム」
クイルの方は、いつものようにふわふわと浮かぶ本を引き連れて、私の後を飛んでついてくるのだった。
「セットセイルは?」
「そのウイルスと戦っていたわ」
「後で説教だな」
「いつもご苦労さま」
メモリ内の部屋同士をつなぐ万華鏡のような通路を急ぎながら、異常な書き込みが行われていないかスキャンする。負荷が大きいから、こういう緊急時だけ実行するプロセスだ。なんといっても、このPCのCPUはシングルコア、使えるメモリも2GBだけなのだから。
不意にスキャンが止まった。メモリ上の疑わしい活動が行われている場所と、影響を受けたファイルのリストが表示される。
「クイル、私の拡張データベースを頼む」
「イエス、マム」
彼女が差し出したのは一冊の巨大な本。ネット上のデータベースからダウンロードした、ウイルス事典のようなものだ。私の製作者たちが常に更新しているし、頻繁に同期しているから、ここに載っていないウイルスはまず存在しない……はずなのだが――
「侵入したウイルスの名前はわかるか?」
「いいえ、残念だけれど」
「チッ、こいつの挙動と一致するものがない」
「えっ?」
「新型のウイルスかもしれない。もしそうなら、捕らえて解析して、会社に報告しないと」
「じゃあ、今回は生け捕りということ?」
「できればな。でも、データを守ることが最優先だ」
「了解」
「敵は近いぞ」
メモリ領域の中には、それぞれのプログラム用にオフィスと私室が確保されているが、ほとんどの場合は広大な青空のもと、草生い茂る地面にパーティションで区切られたデスクが置かれているだけだ。
ただし、常にメモリの一部を占有するようなプログラムの場合は例外。個室を与えられ、内装も自分の好きなように変えられる――といっても、PCがシャットダウンするたびに片付けなければいけないが。
私の部屋は、セキュリティの問題で外の光をシャットアウトし、デスクとベッドを一つの部屋の中に置いて、いわゆる一人暮らしのワンルームのようにしていた。
現場の部屋の前に到着すると、入る前から中の惨状がうかがえた。入り口付近に紙の燃えカスが散らばり、灰が積もっている。ウイルスがそれだけファイルを壊している証拠だ。
まったく典型的な真似をしてくれるが、脅威度としてはそれほどでもない。タチの悪いのになると、ユーザーの心理につけ込むのがいるらしい。セキュリティソフトのふりをしたり、ファイルに暗号をかけて身代金を要求したり……聞くだに恐ろしい所業だ。今回のようにデータをスクランブル化されただけなら、参照ポイントが残っていたり、パターンを推定できたりすれば回復できる。
ただ気にかかるのは、部屋の入り口から熱い空気が流れてきていることだ。大抵のシステムは空気がどんな状態でも問題ないが、熱だけは別。コンピュータというのは熱に弱いものなんだ。
ドアノブに手をかける――ロックされていた。
制御パネルに手を置いて、保護されたメモリ領域にアクセスを試みるが、ドアは閉まったまま。
くそっ! ここを開くには管理者権限が要る。
どうして《ユーザー》は私にフルコントロールを付与しておかないのか。いくら私でも、権限がなければいざという時にできることは限られてしまう。
空中に両手をかかげて目を閉じる。すると、私の前に光輝く球体が現れた。無数のデータが輪となって球の周囲を回っている。光の球はいかにも人工的な口調で話し始めた。
「管理者権限を要求します……3、2、1……」
カウントがゼロになった瞬間、白い光が球体から放たれる。このアクションはほとんどのプロセスに割り込むが、まったく無害だし珍しいことでもない。《ユーザー》が要求を拒否することも稀だ。ただ待てばいいだけ。だから待つ……ひたすら待つ……
「Agnes Computer Protection Suite
はあ……と安堵の息を吐きながら、もう一度制御パネルに手を置く……が、開かない。思わず口から汚い言葉が漏れてしまう。
「一瞬で権限を剥奪されたのかしら?」
「ああ、おそらく……こうなったら強行突破しかないな……」
「ますます熱が悪化してしまわないといいのだけれど……」
「私が気をつけていれば問題ないはずだ」
左手をドアに向ける。姿を現したサイズ・ブルームの柄の部分が消えて、6枚に増えた刃が手の周りを回り始める――!
「《管理者権限実行
加速する刃の回転。
「《保護設定上書き
手のひらから放たれた青い円筒状の光がドアを包む。回転していた刃は一つに収束し、元通りの「ほうき鎌」になって再び左手の中に吸い込まれていった。
青い光が収まったかと思うと、突然部屋の内側からもっと強い光があふれ出した。露わになった部屋の中、芝は茶色に焼け焦げ、空は煙で濃い灰色に染まっていた。煙は浮島の中央にある歪な形の焚き火から上がっているようだ。
変わり果てた光景、その中心――焚き火の横にウイルスらしき存在が立っていた。
「私は《Agnes Computer Protection Suite
相手はいわゆるゴスロリ少女の姿をしていた(《ユーザー》のアクティビティから得た知識だ)。さらりとしたストレートの長い黒髪。同じく黒のドレスとタイツ、消防士のようなグローブとブーツ。手にはファイルをいくつか持っている。そいつは感情の読めない顔でこちらを見るが、返答はない。
「あと5,000サイクル……繰り返す、すべてのプロセスを停止しろ!」
ウイルスが手元のファイルに視線を落とす。焚き火にくべるつもりのようだ。サイズ・ブルームを取り出して両手で握る。これ以上ファイルを燃やされる前に攻撃を仕掛けなければ。
ウイルスはもう一度ちらりとこちらを見て――ファイルを開いて見せてきた。
なんだ? 相変わらずの無表情だが、どこか好奇心を抱いているようにも見える。何のつもりだ? ファイルの中に気になるものでもあったのだろうか。それとも私の気を逸らそうとしている?
足を踏み出そうとしたその瞬間、頭の上から聞き慣れた――鬱陶しい声が響いた。
「見つけたぞクソウイルスめ! たあっ!!」
勢いよく私の目の前に降り立ったのは、ウェブブラウザの『Setsail Navigator
ともかく、このバカは銃剣のついた二丁拳銃を得意げに構えて突撃しようとしている。なんでわざわざ銃で近接戦闘したがるのか、普通は疑問に思うだろうが、それが彼女のスタイルだ。
「おいセットセイル、よくもまた厄介なヤツを持ち込んでくれたな」
「ごめんごめん、ウイルスだとは思わなくてさ~……てへぺろっ」
まったく反省していない。
「笑い事じゃない! どれだけのファイルが壊されたかわかるか!?」
「そういうのはクイルに聞いた方がいいんじゃない? 電卓も起動してないしね~」
そんな適当な返事をしながらウイルスに斬りかかるセットセイル。その瞬間、ウイルスが変異を始めた。
その衣装がまるでCPUに乗せたロウソクのように溶け、手足が鋭い牙と口を持った緑色の触手へと変貌する。ぐるんと白目をむき、口が不自然に大きく開いて……喉の奥から複数の目がついた触手が這い出してきた。
だが、セットセイルは動じない。左手の銃剣が異形の胴体に突き刺さり、右の銃剣は口から伸びた触手を正確に貫いた。ピンク色の血と、少し前まで服だった粘液が飛び散る。銃剣の切っ先がフックアンカー状に変形し、獲物の肉に食い込んだ。両手足の触手の先から上がる鳴き声は、つんざくような悲鳴に似ておぞましい。
「さあいくよ」
ぺろりと口の端を舐め、セットセイルが引き金を引く――
左、右、左、右。一定のリズムで、マザーボードの裏まで届くんじゃないかと思えるほど大きく鳴り響く発砲音。銃撃のたびにウイルスの体が弾き飛ばされそうになるが、がっちりと食い込んだフックがそれを許さない。
ピンク色の返り血を顔に浴びながら撃ち続けるセットセイルの姿は、まるでネットで人気のアニメのようだ。
「うっし、アグネス! トドメやっちゃって!」
「いや、こいつは新型のウイルスかもしれない。生かしたまま検査し、データベースに報告する」
「え~~~、つまんないの。必殺技でドカーン! ってやるとこ見たかったのにさあ」
「ゲームじゃないんだぞ」
「いや、元々ゲームをダウンロードするはずだったからね。せめてこいつで楽しませてもらわなきゃ!」
ウイルスはもはや肉塊に近い状態だが生きており、フックから逃れようともがいている。だが、身動きする度に別々の触手の口から悲鳴が漏れるだけだった。
「ってかキモすぎない? こいつ。こんなの生け捕りとかないわ~」
銃剣が元の真っ直ぐなブレードに戻り、ウイルスがどさっと倒れる。私はすかさず空中に手をかかげた。
「《管理者権限実行
二十面体を形作るワイヤーフレームがウイルスを取り囲み、その動きを止める。そしてウイルスごと一気に収縮し、私の手のひらに収まった。
「あはは、結局凍結しちゃってんじゃん。検査と報告はどうしたの?」
「うるさい。私の仕事に口を出すな」
「まあまあ、そんな熱くなんないでよ。大した被害もなくてよかったじゃん。そっちの『仕事』もさっさと終わらせてさ、ゆっくりしようよ~」
「大した被害って……システムの整合性のことを考えて言ってるのか?」
「いや~、あたしはそういうの興味ないから。《ユーザー》ちゃんと一緒で」
ため息と共にうめき声が漏れてしまうが、セットセイルを責めるわけにもいかない。アドオンは別として、このブラウザにはそもそも基本的なマルウェア対策機能すら搭載されていないのだ。システムに深刻な被害を及ぼすようなことでもなければ、基本的に無防備と言っていい。
仕様上仕方のないことではあるが、それでも、もっとしっかりしろと言いたくなる。でないと、数百万サイクルもしないうちにまたトラブルを引き起こして、私が尻拭いをする羽目になるのだから。
「これから《ユーザー》に報告するのよね?」
そう聞いてきたクイルは、焚き火を片付けるシンプルなプロセスを実行しつつ、焼けたファイルの残骸を拾い集めている。
「ああ、ポップアップウィンドウを出して脅威を隔離したことを知らせる」
「破損したファイルの報告は?」
「そのことだが、壊れたファイルを10億サイクル以内にすべて復元できるか?」
「わからないけど、やれるだけやってみるわ」
「頼む」
クイルと並んで、手のひらサイズに格納されたウイルスを持って部屋を出ようとすると、セットセイルが声を上げた。
「あ、《ユーザー》ちゃんが呼んでる。そのキモいのがいたサイト、また見たいって」
「ポップアップで警告してあげた方がいいのではないかしら……」
「そうだな、そうしよう」
左手から透明なパネルを出現させ、例のサイトを危険なサイトとして登録する簡単なコマンドを打ち込む。これで、ポップアップウィンドウのプルダウンボタンから「無視する」を選ばない限り、サイトへのアクセスをブロックするようになった。
セットセイルは腕を組んでふくれっ面をしているが、システムへの脅威に比べたらそれくらい何でもない。まあ、ウェブサイトを表示することが使命のプログラムとして、それを邪魔されるのが――しかも頻繁に――面白くないのは理解できる。それでも、仕方のないことだ。
「なあ、これまで何度も何度も言ってるけど、怪しいと思ったら必ず私に報告してくれ。頼むから」
と、言ってみたところで意味はないと知りつつ、奇跡が起きないとも限らない。
「はいはい、わかってるよアグネス先生!」
やれやれだ。
***
今回のウイルスについてのレポートを送るために自室に戻っていったアグネスとは別に、私は私で自分の仕事がある。ワードプロセッサーとしてテキストを処理する本来の使命だけではなく、最古参のプログラムとして他のプログラムの手助けをする、いわばボランティア活動だ。
一番関係が深いのは《ファイルブラウザ》。ハードディスクに素早くアクセスできるよう、メモリ内の特定領域に常駐している彼女。私はそのアシスタント司書のような役割を担っている。
あらゆるデータに簡単にアクセスできるように最適化された彼女の部屋は、まるで人間の図書室のよう。金糸で縁取りされた深紅のカーペットに、木目調の机。そしてファイルでいっぱいの棚が立ち並ぶ。ここではメモリとハードディスクの境界が曖昧で、その一体感がとても印象的だった。

「おつかれさま、クイル。ウイルスはどうなった?」
いつものように、彼女はファイルが飛び交う部屋の中央に浮かんでいた。
「アグネスとセットセイルが無事に退治したわ」
「それはよかった」
「全体的なデータの被害はどのくらい?」
「数は多くないけど、一部はかなりひどいね。そこにまとめておいたよ」
「すぐに修復にとりかかるわ」
「ああ、ありがとう、クイル」
ファイルブラウザは忙しい。「ファイル管理」……一見簡単な仕事のように思えるけれど、責任は重大。OSのコアプログラムとして、私たちの誰よりもシステムの根幹に近い。それでいて、常にここでその重要な使命に縛られている。孤独を感じずにはいられないはずだ。
アグネスのデータを参照しながらファイルブラウザがまとめた破損ファイルのリストを確認する。「ピクチャ」、「ドキュメント」、「ミュージック」……あのウイルスは個人用ファイルを狙って作られたもののようだった。この種のファイルは、何かがあればユーザーがすぐに気づきやすい。アグネスが早めにポップアップで知らせておいてくれてよかった。
まずは難易度の低い文書ファイルから修復を始める。元々「ドキュメント」フォルダには全部で96ファイルが存在し、そのうちサブフォルダ下にあるのが72ファイル。84ファイルは純粋な文書ファイルで、残りは様々。その中でウイルスにやられたのは8ファイルのみ、どれも文書ファイルだ。
kadai_ejison.doc
レポート_ポンペイ.doc
国語感想文1.doc
小説アイデア.doc
ラストスターライト.doc
Fluid Angel全ルート攻略.doc
泣き虫の山.doc
イーグル・アイランド.doc
ありがたいことに、あのウイルスのファイル破壊方式は原始的だった。データを見ていくうちにそのパターンにも慣れ、ファイルの「破損」というよりも「暗号化」に思えてきた。
しかも「レポート_ポンペイ.doc」というファイルには、「レポート_ポンペイ2.doc」というほとんど同じ無事なファイルがあったため、その二つを比較すれば「暗号化」のアルゴリズムを特定できる。焼け落ちた解読不能なファイルも、復号化することできれいなファイルに戻っていった。
そのことをアグネスに報告したところ、助かったとすごく喜んでいた。どうやらウイルスの解析で壁に突き当たっていたらしい。誰かの助けになれた――そのことが私は嬉しかった。
復元したファイルをHDDの元の場所に戻していて、ふと気がついた――あのウイルスは何を基準にして攻撃するファイルを選んだのだろう?
私の「最近使ったファイル」というわけでもないし(ファイルブラウザも違うと言っていた)、並び順もばらばら。ファイル名、サイズ、更新日時や作成日時、どう並び替えても隣り合わない。
普通のウイルスは攻撃対象に規則性がある。特定のフォルダを狙うのがよくあるケースだ。
どうにも気になった私は、再度アグネスに連絡を入れることにした。
「ねえアグネス、聞きたいことがあるのだけれど」
「なんだ? どうかしたのか?」
「あのウイルスが攻撃対象を選ぶのに使用したプロセスは特定できた?」
「相変わらず鋭いな」
ため息をつくアグネス。
「ちょうど今それを探っているところだ。まず普通のやり方じゃないな。今のところ、バイナリに特定の文字列を含むファイルをターゲットにしたんじゃないかと思ってる」
「キーワードで検索したのかしら? それなら修復したファイルを調べればすぐにわかるはず」
「いや、こっちでもう調べてみた。ウイルスが狙うような共通の単語は見つからなかった」
「そう……」
「これからポップアップを出す。他に何か気になることはあるか?」
「いいえ、特にないわ」
「そうか、じゃあな」
数百万サイクル後、《ユーザー》に向けて発せられたポップアップメッセージがPC内にこだました。
「Agnes Computer Protection Suite
実際の事の大きさに比べて、すごくあっさりしたお知らせだ。思わず吹き出してしまう。
私たちに対しては歯に衣を着せないくせに、《ユーザー》にメッセージを送る時は別人みたいに奥ゆかしいのがアグネスのかわいいところ。ファイルが「破損」じゃなくて「影響を受けた」という言葉選びも、《ユーザー》を心配させないためだろう。
アンチウイルスソフトのフリをしてマルウェアをインストールさせようとする「スケアウェア」という存在の話を聞いたことがある。PCを回復するために料金が必要と言って騙す手口だ。幸い、これまでこのPCが感染したことはない。私たちのユーザーは少しルーズな人物だけれど、そんな詐欺に引っかかるほどPCに疎いわけではないらしい。
《ユーザー》との付き合いはもう3年になる。だから彼女のこともよく知っている。ロキシー・ガードナー、14歳の女の子。学校の課題や自作小説でよく私を使うけれど、一番使用頻度が高いのはセットセイル。
ロキシーは……何と言うか、ネット上の暴力的なコンテンツが大好きな子。棒人間が殴り合う動画とか、粘土の人形がぐちゃぐちゃに吹き飛んだりする動画をよく見るし、登場人物がひどい目に遭ったりする……少しエッチな二次創作小説も読むこともある。おかげでセットセイルが影響されて、あんな性格になってしまった。
私の持つ限られた情報によれば、ロキシーの行動は人間社会で問題とされるようだけれど、私はただのワードプロセッサー。テキストを編集するのが私の役目であって、フィルタリングしたり説教したりは領分ではない。
そんな私の思考は、お騒がせな彼女の登場で遮られた。
***
「やっほー、クイル。今日のクリップの調子はどう?」
あたしはクイルに抱きついて、ペーパークリップの形をした髪飾りを撫でる。
「今はファイルの修復で忙しいの。《ユーザー》に呼ばれたのではなかったの?」
「うん、例のサイトでゲームをダウンロードしようとしてたんだけどさ、アグネス先生がポップアップで脅かすもんだから、あたし閉じられちゃった。ひどくない~?」
言いながらクリップを外して曲げてみる。
「か、返して! それは大事なものなの!」
「でも《ユーザー》ちゃんはこれ使ったことないじゃん! もったいないよねえ……たぶん形が悪いんだよ。あたしがハート型にしたげる! そんで今度ウイルスと戦う時はさ、こいつをピーンと張って敵にぶっ刺すの! ブシューーッ! って!」
「ああもう、やめなさいったら!」
あたしの手から取り返して元に戻そうとするクイル。もう曲げちゃったから、どう頑張っても綺麗に元には戻らないんだけど。
でも大丈夫! 新品の予備がたくさんあるのは知ってるんだ。本当に一つしかない大事なものなら、さすがのあたしも曲げたりしないっての。
「はいはい、クイルにはハートじゃなくてクリップ型がお似合いだよ。いや、むしろOLのコスプレすべき」
「あなた、どこでそんな知識を仕入れてくるの?」
「二次創作小説投稿サイト! この前のとかすごかったよ。『終末のキャンドル』のヒロイン二人がさ、お互いにロウソク持ってあそこに――」
「わー! わー! それ以上は言わなくていいから!」
着てる服と同じくらい真っ赤な顔を本で隠すクイル。この反応がかわいくて、ついからかっちゃう。
「え~? 《ユーザー》ちゃんがクイルでそういうの書くことだってあるでしょ~?」
「あ、あるけれど……恥ずかしいものは恥ずかしいの!」
QuilleWriter
「クイル、今いいか? 調べてて気づいたんだが、破損したファイルには共通の――って、おい。お前はそこで何をしてる!? クイルを出せ!」
「あー、ちょっと待って。鼻血拭いてあげなきゃ、くくっ」
「セットセイル、起動してないからってうろつき回るんじゃない。他のプログラムに迷惑をかけるな」
「ふんっだ」
腕組みしてそっぽを向く。いつもみたいに皮肉の一つでも言ってやろうと思って口を開いたその時――
「お知らせします。《ユーザー》によりPCのシャットダウンがリクエストされました。各プログラムはメモリ内に割り当てられた領域から速やかに撤収し、ハードドライブ内に移動してください」
「あら、今日はもう終わりみたいね」
そう言いながら乱れた髪と服を整えるクイル。
「クイル、また後で話そう」
「ええ。また次回の起動で」
「それじゃあな」
アグネスからの通話が切れた。
「ねえねえ、なんかいつもよりシャットダウンの時間早くない?」
クイルはすでに手荷物をまとめ始めていた。
「わからないけれど、何か現実世界で用事でもあるのではないかしら」
「そっか~。《ユーザー》ちゃんがピピンちゃんを使ってたら何の用事かわかるのになあ」
「まあ、推測の域を出ないけれど」
「クイルさあ、気になんないの? あたしたちのご主人さまのこと。見るサイトで性格とか変化とかはわかるけど、《ユーザー》ちゃんと実際に話せたらなあっていつも思うんだ」
「私は別に、彼女の書く文章とか、他の子の話からわかる情報だけで満足しているわ。《ユーザー》は10代の女の子。他の人間たちと同じように、複雑なね」
「じゃあさ、もし話ができるとしたら、何を伝えたい?」
「考えたこともないわね。プログラムとしての役割を越えてユーザーとコミュニケーションを取るなんて不可能だもの。考えるだけシステムリソースの無駄よ」
「ちぇ~っ。《ユーザー》ちゃんと違って、プログラム連中はどいつもこいつも頭が固いんだから」
「このPCにはゲームがたくさん入っているでしょう? 仕事の邪魔ばかりしていないで、ゲームの子たちと遊んでいたらどう?」
ゲームの子たち……最近怒らせちゃったところなんだよなあ……原因は……まあ、あれだ。「スク水事件」とでも名付けておこう、うん。
そんなわけで、あたしはただ笑ってごまかし、自分の部屋に戻るのだった。
ロキシー、気をつけていってらっしゃい、ってね。
***
いつものように、ハードディスクの駆動音と冷却ファンの風切り音で目が覚める。PCが起動するこの瞬間はいつも心地良い。
ただし、目覚めとともにこなすべき大事な仕事がある。電源が切れている間はウイルスに感染することはないが、OSの起動プロセスが改変されていないか起動時に確認しなければならない。
サイズ・ブルームを忘れずに持って、ハードディスク内の自室を出る。やることはほとんどただのパトロールだ。いつもバックグラウンドで動いてるプログラムとプロセスは覚えているから、何かあればすぐにわかる。
通常のプログラムの中にも、すでに準備ができているものがいる。ユーザーが望んだ時にいつでも使えるようにするためだ。
その中の一つが、ピピンこと『Pippin
《ユーザー》は他の人間とのコミュニケーションに別のハードウェア――携帯型の小型端末を使用している。セットセイルによれば、ネット上の人間とウェブサイトで直接やり取りをすることもあるらしい。
ピピンはこのPCのプリインストールソフト――最初から入っていたプログラムで、最初のセットアップも済んでいるが、ほとんど使用されたことがない。
一度セットアップを済ませているという事実が、今もピピンに望みを持たせているのだろう。OS起動時に自動的に起動する「スタートアップ」という、全プログラム憧れのリストにも入っていて、また使われることを期待しながらいつもバックグラウンドで待機している。
《ユーザー》は、使わないならどうしてアンインストールしないのだろうか。不要ならハードディスクから削除するのが一番快適ですっきりする。気に入らないソフトに対して、彼女も普段はそうしているのに。
「あっ、アグネスさん。《ユーザー》さん、今日はわたしのこと使ってくれますかね?」
「期待はしない方がいいと思うぞ」
「うう……」
しょんぼりと下を向くピピン。何度も同じやり取りをしているとはいえ、冷たい言い方かもしれない。だが、それ以外に一体何を言える?
通り抜けざま、彼女をスキャンする。ウイルス検出なしだ。
「検出なし。ピピン、使われるといいな」
「ありがとうございます!」
健気に笑顔を向けてくる。こんなに良い子なんだ、セットセイルなんかよりも報われてほしいが……
「おっはよ~! 調子どう~?」
はぁ、本人のご登場だ。返事にCPUパワーを使うのもバカバカしいので、淡々と答える。
「起動時のチェックが無事に終わったところだ。これから例のウイルスのレポート作業に戻る」
「相っ変わらず仕事ばっかだね~アグネス先生は。やっほ~ピピンちゃん、元気~?」
「おはようございます、セットセイルさん! 元気です! 《ユーザー》さん、今日はわたしのこと使ってくれますかね?」
「ん~、どうかなあ。でもね、デフォルトのページを初期状態に戻しておいたよ! あたしたちの開発会社のページ! 最近、ピピンの新バージョンを大々的に宣伝してるみたいだから、もしかしたら《ユーザー》ちゃんもその気になるかもねっ」
「えっ、本当ですか? わ、わたしのために?」
「ふっふーん! 困ってるプログラムを放っておけないかんね!(^-^)」
それを聞いて、口を挟まずにはいられなかった。
「いつも私に迷惑かけてるヤツがよく言う。クイルにも前回――」
「いやいや、クイルはあれで喜んでんだって!」
周りを見回し、他に誰もいないことを確認して続けるセットセイル。
「ただ認めたくないだけ。アグネスみたいな人相手には特にね」
ウイルスを持ち込むことに文句を言ってやろうと思っていたが、出鼻をくじかれてしまった。
「まあともかく、今後は協力するように。なぜだかお前は顔が広いんだから」
「またまた、アグネス先生にあたしの協力なんていらないっしょ。ピピンちゃんみたいに、かよわ~い子ならともかく」
ピピンを抱き上げ、ぬいぐるみを抱えるかのように密着したまま振り回すセットセイル。
「ああ~ピピンちゃんかわいすぎだろjk! 萌えるお~」
この珍妙な言葉遣いは最近の流行らしく、よくわからないがセットセイルは好んで使っていた。
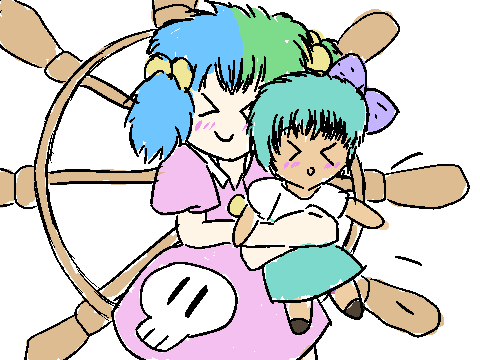
だが、この二人のツーショットは絵になる。同じ会社の製品だからだろうか、すごく自然だ。セットセイルは、頬ずりしたり頬をつっついたりと、好き勝手にかわいがっている。なんとなく温かな気持ちになって、そのまま様子を眺めていたら……ピピンの様子がおかしいことに気がついた。
無表情。最初はそういうリアクションなのかと思ったが、嫌な予感がする。
「おい、放してやれ。ピピンが窒息する」
「え~~? これまで最長記録5分抱きしめてたことあるけど、全然問題なかったよ。ピピンちゃんは、や~らかくて抱っこしやすいように出来てまちゅもんね~?」
抱いていた力を緩め、ピピンの顔を見るセットセイル。
「あれ? ピピンちゃん? なに変な顔してんの? おーい?」
目の前で手を振るも、反応はない。ぺしぺしと顔をたたいても同じだった。
そして、いきなり背筋が凍るような言葉がピピンの口から飛び出した――
「Pippin
ストン、と地面に落ちるピピン。力なく部屋のドアにもたれかかり、かすかに目が光るだけで、まるで命のない人形のようだ。
なんだ? 何が起こった?
サービス終了だって?
バカな……何の前触れもなくいきなり使えなくなることなんて……前例がないわけじゃないが、ひどすぎる。セットセイルを見ると、唖然としていた。
「え、え……? 嘘でしょ……」
両手で口を抑えてつぶやく彼女。そして手を下ろし――
「なんで? 北米で利用者数第3位の人気メッセンジャーじゃないの? なんでいきなり終わらせるの!? ITバブル崩壊の影響なんてとっくに終わってるし、会社の株価も悪くないのに。タチの悪い冗談? まさかウイルスにやられたの?」
こちらを向いたセットセイルは、これまで見たことがないほど殺気立っていた。
「アグネス、答えて。ウイルスのせい?」
「まだ解析は終わっていないが、あのウイルスがピピンのプログラムを操作した可能性は低い。破損したファイルのあるフォルダは遠いし、ピピンを狙うような挙動は一切見られない」
「そんな……じゃあホントに捨てられたってこと? クソッ! 誰だよ決めたやつ! あたしが八つ裂きにしてやる!!」
いきなり二丁拳銃を取り出すセットセイル。バイオリンに似た独特のチャージ音が高まっていく。
「落ち着け、まずは事実を把握しよう。勘違いかもしれない」
二丁の銃にそっと手を乗せてなだめる。すると、衣服と本が風を切る飛翔音が聞こえてきた。クイルだ。
「アグネス! 様子がおかしいの」
実際に地に足をつけて走ってきたわけでもないのに、マザーボードを一周したかのように汗をかいていた。
「どうした?」
「ええと、辞書のインターネット更新をしたら、いきなり大量の単語が入ってきたの。最初は辞書の外注先を変えたとか会社が大きな更新を入れたのかと思ったのだけれど、いきなりそれもおかしいと思って、新しい単語がいつオンラインのデータベースに登録されたのか調べようとしたら、《システム時計》が大声を上げながら通路を走ってきて。なんとか落ち着かせて聞いてみたら、ネットと同期した日付と時間が前回と大幅に違っていたらしいの。内蔵時計の電池が切れたような症状だけれど、残量を確認したら実際は生きていたし、シャットダウン前に保存したファイルの日付も私の記憶と同じで――」
「待て待て、要するにどういうことだ?」
「辞書の新しい単語の日付と、時計のインターネット時刻が完全に同じなの。だから……もしかすると、ものすごく長い間電源が入っていなかったのではないかしら」
「じゃあ……」
セットセイルの表情が怒りから不安に変わる。
「どのくらい電源が入ってなかったっていうの?」
「このPCのCPUは2.2GHzだから、約1.0432941e+18サイクル――人間の時間にして4億7422万4601秒、つまり5488日。今日は人間の暦で2023年3月7日。私たちは15年間眠っていたことになるわ」